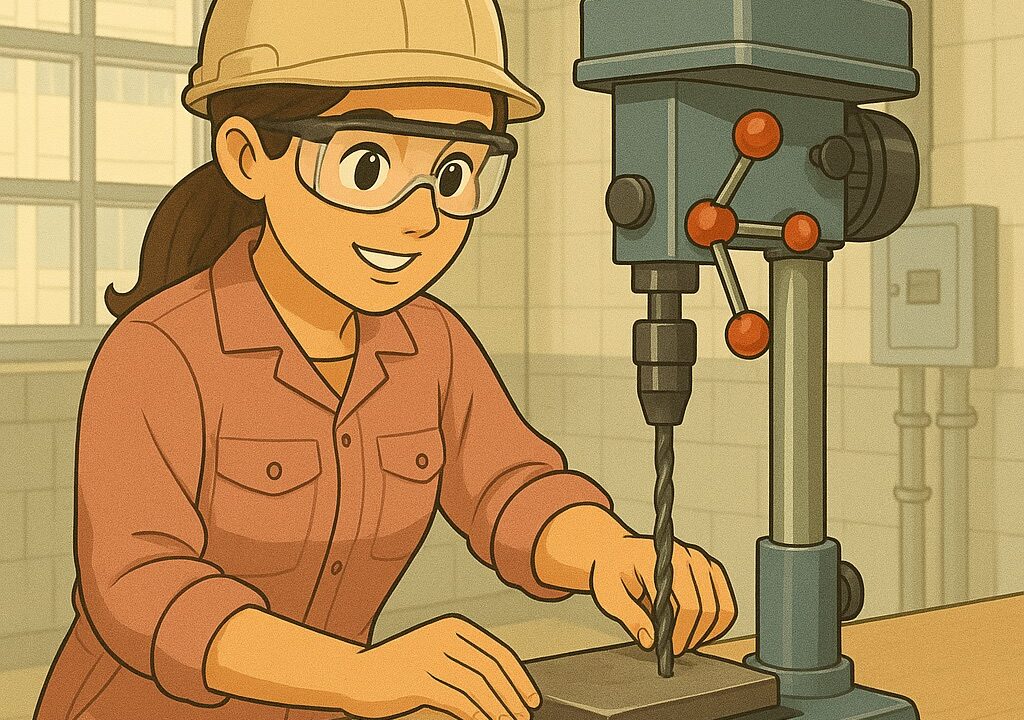今回のテーマは「ドリルとボール盤」です。
アルミ・鉄・ステンレスといった金属に穴を開ける際、「ドリルを使う」ということは、多くの方がご存じだと思います。
ですが、その“ドリルとボール盤の組み合わせ”、本当に合っていますか?
実は、金属の種類や穴の大きさによって、ドリルの選び方やボール盤の使い方には、ちょっとした“コツ”があるのです。
結論! ドリルの径に合わせて、ボール盤の回転数を変更するべし!
まず結論です。
穴のサイズ(ドリルの径)が大きくなるほど、ボール盤の回転数は下げる必要があります。これは、ドリルが材料(ワーク)に接触する“外周のスピード”(周速)が速くなりすぎると、刃先に過度な摩擦と熱が加わり、刃が傷んでしまうからです。
特にステンレスのような熱を持ちやすい素材では、回転数が速すぎると焼き付きや変色、変形などのトラブルにつながります。
しかし、鉄鋼ドリルでも正しい回転速度と送り速度を見つけることが出来れば、HSSドリルのような汎用ドリルでも、ステンレスのような材質にも容易に穴を開けることが出来ます。
ドリルの径(大きさ)に対して、回転数を合わせないとどうなる?
- ドリルの刃がすぐに摩耗・破損する
- 穴が真円にならず、仕上がりが悪くなる
- 加工熱によって材料が変色・変形してしまう
こうしたトラブルの原因になります。
では、順を追って詳しく見ていきましょう。
ドリルの種類と適切な機械を使い分けよう
”ドリル”と言っても、種類はいろいろ
兼用できるものもあれば、用途に特化して設計された専用タイプも存在します。

たとえば、木材相手なら「鉄工用ドリル」でも穴を開けることは可能です。
ですが、その穴の仕上がりは、どうでしょうか?
表面は問題なく見えても裏側はバリだらけだったり、加工中に木材が徐々にボロボロになってしまったり、木材が焦げてしまった…なんて経験はありませんか?
木材に穴を開けるために使う「木工用ドリル」は、バリ(かえり)が少なく、きれいな仕上がりになるよう工夫された専用のドリルです。
では、コンクリートの場合はどうでしょう。
木工用や鉄工用のドリルでは、当然ですが穴を開けることはできません。
そこで「コンクリートドリル」の登場です。
これを電動ドリルに取り付けて…さあ穴を開けよう!――残念ながら、これも失敗します。
正しい組み合わせは、「コンクリートドリルをハンマードリルに取り付けて使用する」こと。
つまり、適切なドリルを、正しい機械に取り付けて使うことで、初めて素材に合った正しい穴あけが可能となるのです。
鉄鋼ドリルとボール盤
今回は鉄鋼ドリルとボール盤に焦点をあてて解説していきます。
その名の通り、鉄に使用するドリルなのですが、実はとても奥が深い工具なのです。
鉄鋼ドリルの「奥の深さ」って、何?
「鉄鋼ドリル」とひと口に言っても、実は形状や材質、コーティングの種類などによって性能や用途が異なります。ここではドリルの選定について解説してみたいと思います。
ポイント①:ドリルの材質(ハイス鋼、コバルト、超硬など)
- ハイス鋼(HSS):汎用性が高く、DIYでもよく使われる。コスパ良好
- コバルト入りハイス鋼(HSS-Co):硬度と耐熱性が高く、ステンレスにも対応
- 超硬ドリル:工場やプロ向け。超硬合金製で非常に高硬度。高価で諸刃の剣
ポイント②:先端形状(シンニング加工、先端角度など)
切りくず排出と切れ刃の強度に影響を与えます。ねじれ角が小さいほど、硬く脆い材料に適しており(切れ刃が強い)、ねじれ角が大きいほど、軟らかく粘着性のある材料に適しています(切りくず排出性が良い)。
- シンニング加工:芯ブレしにくく、まっすぐ穴が開けやすい
- 先端角度:例えば118度は汎用向け、135度は硬い材にも対応
ポイント③:コーティング(チタン、黒染めなど)
コーティングは、ドリルの寿命延長、切削速度の向上、表面仕上げの改善につながります。
- チタンコーティング:摩耗しにくく、滑りも良くなる
- 黒染め(ブラックオキサイド):切削油とのなじみがよく、摩擦熱を抑える
ここで、お伝えしたいことは、あなたがどういう加工をしたいか?ということです。
例えば、まっすぐで奇麗な穴を開けたいのか?それとも、硬い材質のものに穴をあけたいのか?それとも、穴さえ空いていればいい(バカ穴)のか?など、ドリルの選定をするの大事なところです。
もちろん、材質にもよりますが、アルミニウムのように柔らかい金属に精度のいらない穴を高価な超硬ドリルを用いて穴開けをすることは、いささかオーバースペックというものです。
つまり、ドリルは消耗品ですので、コストも気にしなければなりません。
そのようなことからも判るようにドリルの選定とは加工単価を考える上でも需要なファクターと言えるのです。
| ドリルタイプ/材料 | 主な特性 | 推奨ワークピース材料 | 推奨用途/穴タイプ | 主な利点 | 一般的なコスト影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS (高速度鋼) | 靭性、汎用性 | 一般鋼、アルミニウム | 汎用、粗い穴 | 費用対効果が高い、入手容易 | 低 |
| HSS-Co (コバルトHSS) | 耐熱性、耐摩耗性向上 | ステンレス鋼、高張力鋼 | 硬い材料、汎用、深穴 | HSSより耐久性、汎用性向上 | 中 |
| 超硬 (Carbide) | 高硬度、高耐摩耗性、脆性 | 硬化鋼、鋳鉄、特殊合金 | 高精度、高速加工、難削材 | 高性能、長寿命、高精度 | 高 |
| PCD/cBN (先進材料) | 極高硬度、高耐摩耗性 | 非鉄金属、焼結材、鋳鉄 | 超高精度、極難削材 | 極めて高い性能、長寿命 | 非常に高い |
鉄鋼ドリル×ボール盤の基本的な使い方
今回は「鉄鋼ドリル」をボール盤で使う場面を想定してお話ししています。
鉄鋼ドリルを使うときの基本ポイントは、以下の3つです。
① 回転数を下げる
大きな径ほど、ゆっくり回すのが鉄則。以下は目安です:
| ドリル径(mm) | 鉄への穴あけ回転数(rpm) |
|---|---|
| ~3mm | 約1500~1000 |
| 3~6mm | 約1000~600 |
| 6~10mm | 約600~400 |
| 10~13mm | 約400~300以下 |
| 13mm以上 | 300以下 |
※ステンレスではさらに低回転が推奨されます。

↑卓上ボール盤の回転変更の例
このタイプは本体の裏のモーターでベルトのテンションを張っているので、それを緩めて、任意の回転数の位置にベルトを掛け替えます。このボール盤のベルトは1本ですが、2本掛け替えるモデルもあります。ほとんどの場合、カバーの裏や本体の表面に回転数と掛ける位置が記載されていますので、そちらを参考にして下さい。
あと、指を挟まないように気をつけて下さいね。挟むと結構、痛いですよ(笑)
② 切削油を使う
切削油(クーラント)を使うと、刃先の冷却・潤滑ができ、焼き付きや刃の摩耗を防げます。また切削油が無い場合、霧吹きに水を入れて使用するのも効果的です。
穴あけや、切削加工は、冷やすことが大事なのです。
特にステンレスや厚い鉄板には、効果的です。
③ 適切な押し込み圧(送り)を意識する
押し込みが弱すぎると刃が滑ってしまい、摩擦で焼ける原因に。
逆に強すぎても刃が折れるので、“削れている感覚”がある適度な圧力で作業するのがコツです。そして、もう一つ、重要な要素があります。
それは、”音”です。
私の中ではこれが最も重要だと思っていて、適切な回転と送りが出来ている時は、ほぼ無音(ボール盤のモーター音のみ)の状態で加工することが出来ますです。
しかし、回転や、送りが正しくない、ドリルの刃が摩耗している/欠けている、といった加工条件が1つでも狂ってしまうと、金属が擦れる音や、ゴリゴリ音など不快で、恐怖を感じる音(壊れそうな音)という音が聞こえてきます。
ボール盤での穴あけ加工は、かなり感覚を伴うことが多い作業ですので、文字だけでは伝わらないところではありますのが、適当な廃材があれば、色々な回転数で実験してみるのもオススメです。
まとめ
最初の結論にもあったように、ドリルの径が大きくなるにつれて、回転数を落として行くことが大事ということです。
最後まで読んで下さった方へ、古から伝わる呪文を授けます。
それは、 ”6mm、600rpm” です。
これさえ覚えておけば、ほぼ適切な穴加工が出来るでしょう。
・6mmより小さい穴は600rpmより回転を上げる
・6mmより大きい穴は600rpmより回転を下げる
これが呪文であり、今回、最も伝えたかったことです。
多くの方が、ボール盤の回転を変えるのを面倒くさがってしまい、前回加工したときの回転数のまま、作業する人を多く見かけます。しかし、これを実践するだけでも同じ作業でも、差がつきます。
たかが穴、されど穴 なのです。
ちなみにステンレスの場合は、鉄の回転数から100rpmほど下げて加工すると上手くいきます。
回転する機械は非常に危険ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
バイスでワーク(材料)を固定する際も、安全を最優先にしっかりと固定しましょう。
特に長い材料を固定する場合は、下に敷物や治具を使用し、ワークが安定するよう心がけてください。
また、治具の製作については、こちらの記事で解説しています。作業のヒントとしてぜひご覧ください。
>>ゴミが道具に変わる!初心者でも作れる治具のアイデア
今日も一日、ご安全に!